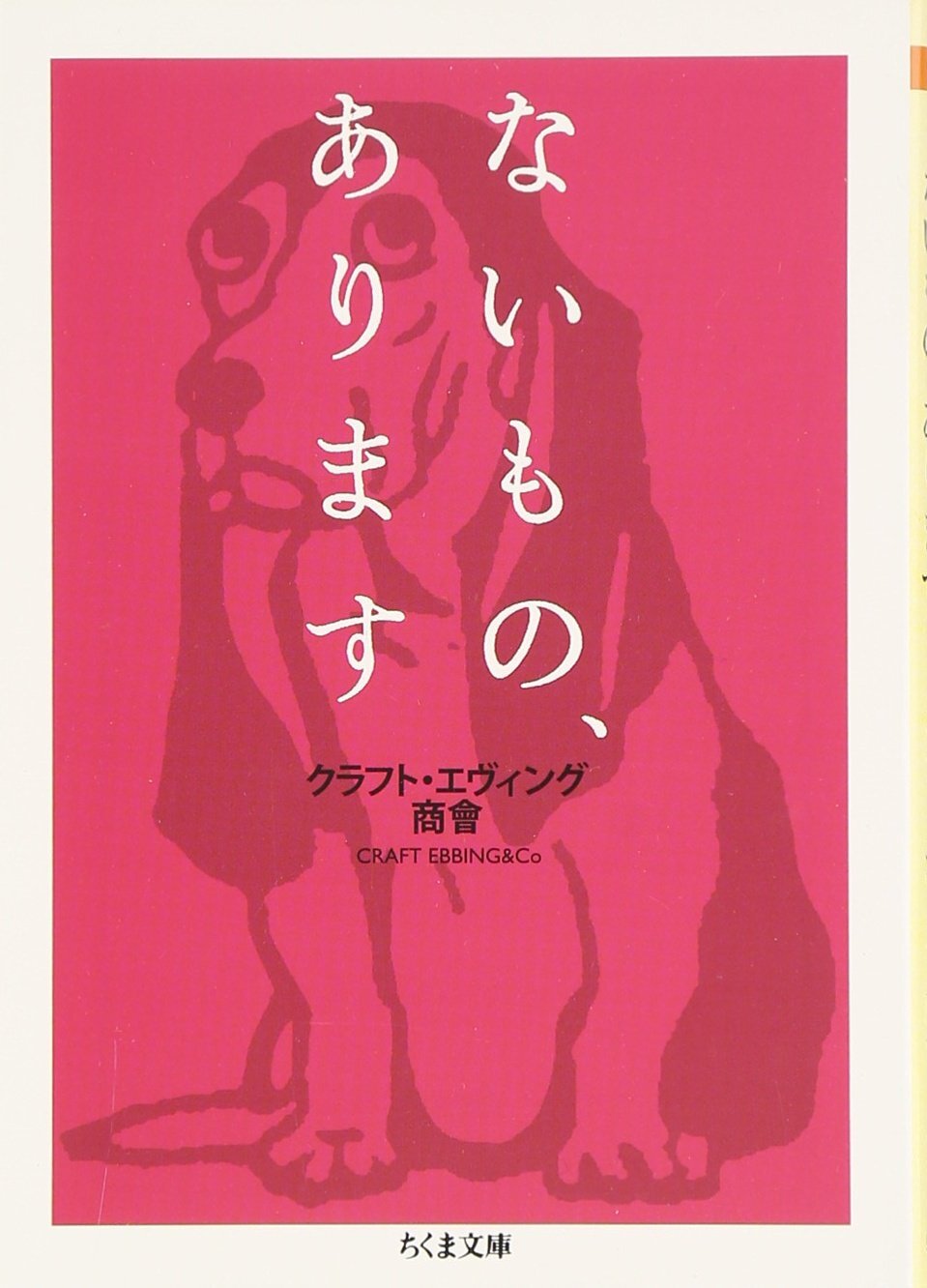RECOMMEND おすすめ
第5回PUSH!1st.「ないもの、あります」

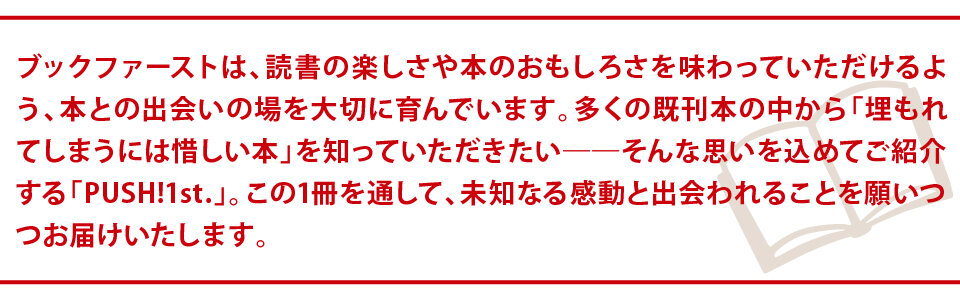
ユーモラスな日本語を楽しんでください。
きっと思わずクスッとなりますよ。
ないもの、あります
クラフト・エヴィング商會/筑摩書房/990円(税込)
よく耳にするけれど、誰ひとり一度としてその現物を見たことがない。そういうものがこの世にはあります。たとえば、持ったことがない〈転ばぬ先の杖〉、あるいは、切れる音を聞いたことがない〈堪忍袋の緒〉、または、あおいだことがない〈左うちわ〉、そして貰ったことがない〈冥途の土産〉。こういうものは、どこに行ったら手に入れられるのでしょうか?このような素朴な疑問とニーズに応え、この世のさまざまなる「ないもの」たちを、古今東西より取り寄せて、読者の皆様のお手元に届けてくれます。 ブラックユーモアが効いた一冊。
在庫を見る
著者来歴

吉田篤弘、浩美によるユニット。著書に「クラウド・コレクター」(筑摩書房)、「おかしな本棚」(朝日新聞出版)など。吉田音名義でも作品を発表しているほか、それぞれの著作も多数。装丁家としても活動し、ちくまプリマー新書(筑摩書房)などを手がける。2001年に講談社出版文化賞ブックデザイン賞を受賞。
著者/クラフト・エヴィング商會さんのインタビュー

――この作品を作られたきっかけを教えてください。
篤弘さん:たとえば、「左うちわって何?」と聞くと、皆さんいろいろな説明をされるでしょう。なかには、いかにももっともらしいことを教えてくれる人もいます。でも、改めて辞書を引いてみると、全く違うことが書かれていたりするんですよね。言葉はあまりにも日常に溶け込みすぎていて、よくよく考えると本当の意味を知らずに使っていることが沢山あります。僕たちは実は無知であるということにおもしろさを感じてこの本を作りました。
――言葉に焦点をあてられたわけは何ですか?
篤弘さん:言葉というのは、実は日常のなかでみんながいちばん使っているモノなんですね。当たり前のものになっているので、普段はいちいち点検したり、注目したりする機会がありません。だからこそ意識的に、言葉というものに対して目をむけてみよう、と。
――ご夫婦でどのように作品づくりをすすめられたのですか?
篤弘さん:文章を担当するのは僕で、彼女はイラストレーションをつくっています。ただ、実作業に入る前に、台所のテーブルを囲んで、ごはんを食べながらいろいろと話し合って、内容をかためていきました。その段階では辞書は見ません。2人とも答えを知らないままにいろいろと話し合うんです。たとえば、「地獄耳ってどういうことかな」ということを、自分たちの想像で「こういうことなんじゃない?」というように、思いつくままに話すのです。そこでテーブルの上にのった言葉が、そのまま文章になっているという感じですね。
――目に見えないものを表現するのに、難しかった点は何ですか?
浩美さん:それぞれの商品のイラストです。見たことのないものを、できるだけ想像の余地があるように絵にするのが、最も難しかった点です。最終的には「ただのうちわだよね」「単なる壺じゃないか」という、ニュートラルなものに落とし込むようにしていましたね。
篤弘さん:「針千本」のイラストなんかも、実際に針が千本あるんですよ。子どものころに「針千本飲ます」と言っていましたけれど、実際につくってみるとぞっとしますね。でも、このばかばかしさが気に入っています。

――イラストはこの作品の大きな見どころですね。そのほかの見どころはどこでしょうか?
篤弘さん:ひとつは、、師匠と呼べる存在の赤瀬川原平さんに、ボーナストラックともいうべき文章を寄せていただいたことです。
また、紹介している「商品」はどれも便利で、あったらいいなと思うようなものなのですが、それを手に入れると、苦しみや人間の業がおまけのように付いてくるという落とし穴があるんです。商品の持つ「毒」を落語のように楽しめると思います。
――クラフト・エヴィング商會として、今後どのような本をつくりたいですか?
篤弘さん:本当にあるものに目を向けています。今まで目に見えないものを表現してきたので、今度は実際にあるものを見せて「本当にそんなものがあるんですか?」と読者を半信半疑にさせる。オオカミ少年になってしまったことを逆に利用して、本当にあるものを、もう一度違う目で見ていただくということをやってみたいですね。そうして見ていくと、ないものもあるものも同じじゃないか、と最終的に言いたいんだと思います。
――ありがとうございます。さて、クラフト・エヴィング商會の書籍はどれもすてきですが、紙の書籍の魅力をどのようにお感じですか?
篤弘さん:本は、通勤や旅など移動のときに携えて日々を前に進んでいく、生きていくということについてのお守りだと思います。あるいは、先生や友だちだったり――、道行(みちゆき)をともにしているものである、と。そう考えると、お守りをダウンロードして満足する人はなかなかいないと思うんです。物体として懐に入れておきたい、手元にあることが、安心であり、魅力であると思います。
浩美さん:そうですね。それと、私は基本的に「紙」が好きで、「本が紙でできていたから、本が好き」というところもあります。
篤弘さん:昨今は電子書籍が話題ですが、少なくとも今はどれだけ紙の書籍に近い形で楽しめるかというところからはじまっていますよね。紙をめくるように次のページにいけるとか。なるべく紙に近いものにしよう、ということは、その時点で「紙の書籍以上のものはない」と言っているようなものですよね。
――では、書店の魅力についてはどのようにお感じですか?
篤弘さん:本というのは、大げさにいうと、混沌とした言葉の羅列です。一冊のなかにいろんな言葉が入っていて、いろんな思いや考えがあって、とても混沌としているものだと思うんです。インターネットのなかにも、ものすごく混沌としたものがあるわけですが、異様なほど際限なく混沌が続いていくものですよね。便利で魅力的ですが、その際限のなさに、いずれみんな負けていくと思います。一方で本は、その混沌にある程度の輪郭があり、人が「混沌」と接するのにほどよく限定されたサイズになっています。本屋さんには、それが拡大されたものであってほしいと思います。自分がまだ知らないことが混沌としてあって、予期しない状態でアクセスできるのは、本屋さん以外にはないと思うんですよね。毎日新しい本が加わり流動している、未知でほどよく混沌としていることが書店としての魅力ではないでしょうか。
――好きな本、影響を受けた本について教えてください。
篤弘さん:これはたくさんあるのですが、僕はまず向田邦子さんの『父の詫び状』ですね。文章を書くことを志したきっかけともいえる作品です。
浩美さん:私は池田晶子さんの本には非常に影響を受けましたが、最近では、井上雄彦さんの『バガボンド』ですね。
――関西と阪急電車にまつわるエピソードを教えてください。
篤弘さん:実は、2人とも関西が大好きで、学生のころからよく関西へ旅行していました。たびたび阪急電車にも乗りましたよ。阪急電車は沿線の風景がいいですよね。窓から見ていると、どの駅にも降りてみたくなります。実際、三宮をはじめ芦屋川、夙川、岡本......、それから宝塚や四条河原町のほうへも足をのばしました。関西にはさまざまな電車がありますが、乗っていて一番落ち着くというか、安心して気持ちよく乗れるのは阪急電車でしたね。