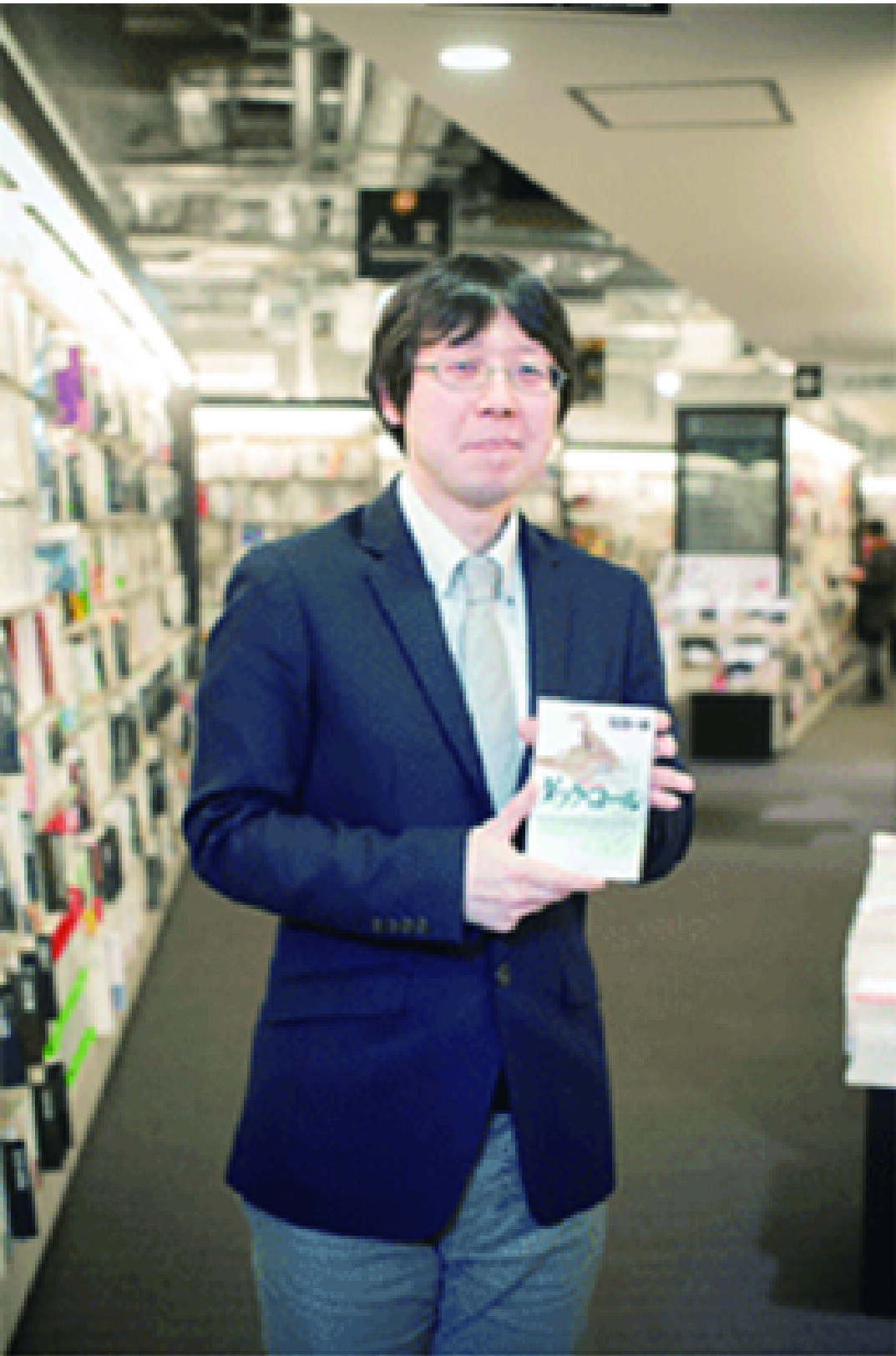RECOMMEND おすすめ
第5回PUSH!1st.「ダック・コール」

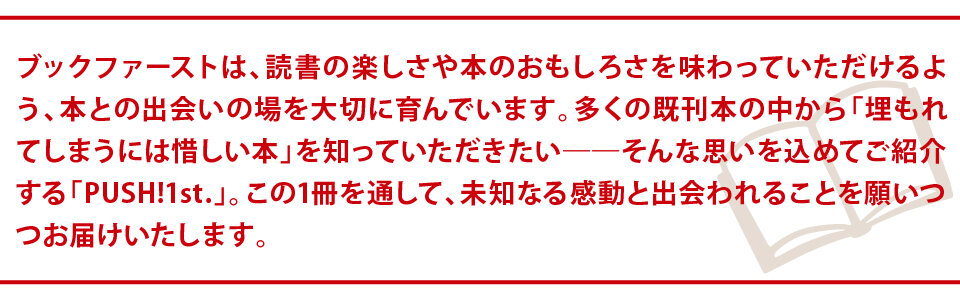
息をのむ美しさ。
人生と自然の豊かさに心を揺さぶられる傑作。
ダック・コール
稲見一良(いなみ いつら)/早川書房/814円(税込)
石に鳥の絵を描く不思議な男。あてどなく歩き、河原の石に絵を描くという。彼に出会った青年は、まどろむうち鳥と男たちについての六つの夢を見る。絶滅する鳥たちの哀しい運命、少年のパチンコ名人と中年男の密猟のひとときの冒険、脱獄囚を追って展開する緊迫の山中でのマンハント、人と鳥と亀との漂流譚、デコイと少年のせつない友情......。
レイ・ブラッドベリの『刺青の男』にインスピレーションを得た、ハードボイルドと幻想が交差する美しき異色作品集。狩猟や銃に造詣の深かった著者が渾身の力で描き出した第四回山本周五郎賞受賞作。
在庫を見る
著者来歴
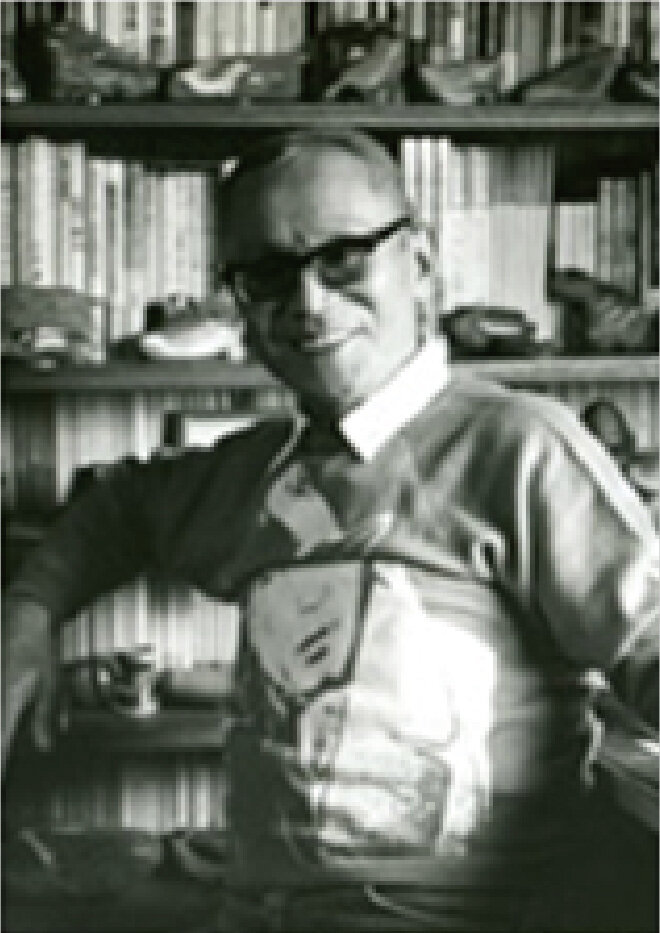
写真:ご家族提供
1931年、大阪生まれ。テレビCFなどのプロデューサーを経て、肝臓がんの発病を機に1985年より作家活動に専念。著書に「ダブルオー・バック」「ソー・ザップ!」「セント・メリーのリボン」などがある。1991年に「ダック・コール」で第四回山本周五郎賞に輝く。病と闘いながら執筆活動を続け、1994年に63歳で没した。
編集者/吉田智宏さんのインタビュー

――この作品とはどのようにして出会われましたか?
吉田さん:本文の活字のサイズを大きく、読みやすくするために、あらためて全体を読み直す機会がありました。このときに担当として、この作品と向き合うことになったのですが、まず私がこれまで読んできたハードボイルドとは印象が違うことに驚きました。ハードボイルドというと、かっこいいとか、タフというイメージがあると思いますが、この作品は、リリシズムや素朴さ、優しさ、温かみのほうが強く、新しいハードボイルド、という印象を受けました。
――この作品の魅力はどんなところにあるとお感じですか?
吉田さん:この作品には、いくつもの出会いと別れが描かれています。報われない主人公たちが、鳥や子どもと出会い、交流をして、立ち直っていく。そこには必ず別れというものがつきまといますが、別れが訪れるころには、出会った時の孤独ではなく、自分のなかに確固たる何かを得られている。そんな、人生のひとつの通過としての出会いを教えてくれるお話です。別れることの悲しさや寂しさを引き受けて、そこから前向きに生きていく。読んだあとにそういう気持ちになれる作品ではないでしょうか。
――鳥と男たちのいくつかの物語が展開しますが、特に好きなお話について教えてください。
吉田さん:私が特に好きなのは、第三話の「密漁志願」と第六話の「デコイとブンタ」です。「密漁志願」は、がんにおかされていた男が、パチンコ名人の少年に猟のやり方を教わって狩りを覚えていく物語です。年の差を超えたふれあいや温かみのあるハードボイルドにひきつけられます。「デコイとブンタ」は、猟の囮に使う鳥の模型、デコイの一人称で書かれたお話で、打ち捨てられていたデコイが孤独な少年に拾われ、2人の交流が芽生えていくというものです。孤独な存在の彼らが出会うことで、立ち上がり、前向きに生きていくところが温かく描かれていて、読んでよかったと思わせる一話です。この作品の全体を通して言えるのですが、報われない人たち、報われないものに対しての温かいまなざしというものが、稲見さんの文章にはあふれていて、同じような境遇にある人は特に共感を得られると思います。
――吉田さんはどのような点で共感されましたか?
吉田さん:私は父親をがんで亡くしたので、第三話の「密漁志願」は自分の父親を重ねて読んでいましたね。みなさんにもこの作品に出てくるさまざまな別れと似たような経験があると思います。大切な人と別れたとき、自分が孤独に陥ったときに読むとすごく響くと思います。また、この作品は、プロ意識を感じ取れる一冊でもあります。第一話の「望遠」が特にそうなのですが、自分がこれだと思ったことは自分で引き受けて責任をもってやる、そういうことの潔さがすごく感じ取れる作品です。仕事をしていて現状に不満があったり、悩んでいるときに読むとすごく勇気づけられると思います。

――優しさや温かみのある作品を残された稲見先生ですが、そのお人柄について教えてください。
吉田さん:私は父親をがんで亡くしたので、第三話の「密漁志願」は自分の父親を重ねて読んでいましたね。みなさんにもこの作品に出てくるさまざまな別れと似たような経験があると思います。大切な人と別れたとき、自分が孤独に陥ったときに読むとすごく響くと思います。また、この作品は、プロ意識を感じ取れる一冊でもあります。第一話の「望遠」が特にそうなのですが、自分がこれだと思ったことは自分で引き受けて責任をもってやる、そういうことの潔さがすごく感じ取れる作品です。吉田さん : 稲見先生は10年におよぶ闘病の間に手術を3回、入退院を19回もくり返されたそうです。残念ながら私は、先生がご存命の間にお目にかかる機会はなかったのですが、稲見先生はご自身の趣味として狩猟をしておられ、銃はもちろん、鳥にもとても詳しかったそうです。この『ダック・コール』という作品には石に鳥の絵を描く不思議な男が登場しますが、稲見先生ご自身も石に鳥の絵を描いておられ、現物が残されています。
また銃のエッセイを連載されていた際には、海外のミステリー作品を取り上げて、銃についての描写が足りないことを指摘したり、いろいろな銃に対して思い入れをたっぷり書かれていて、稲見先生がご自身の豊富な知識に誇りや矜持をお持ちだったことが感じられます。 一方で、とても謙虚な方でもあったようです。稲見先生はこの作品で第四回山本周五郎賞を受賞されていますが、ご自身は受賞するとは思っておられなかったようで、また、愛読していた好きな作家の名を冠した賞を受賞できたということで、非常に感動されていたそうです。
事をしていて現状に不満があったり、悩んでいるときに読むとすごく勇気づけられると思います。
――稲見先生が生きた証として作家活動に打ち込んだわけをどのようにお考えですか?
吉田さん:当時の日本のミステリー界において銃に肉迫するものがなかったことに対して、銃についての知識がある自分が書くのだ、生きた証として小説を残そうという強いお気持ちが、稲見先生の作家活動を後押ししたのではないでしょうか。また、稲見先生は文章に対する美学がすごく強くあるのだなと感じます。著述のなかでも、「抒情するために叙事しなければならない、なんていうつもりはないが、的確でヴィビッドな細部描写に出会うことは、小説からストーリー以外のなにかを楽しもうとする読者にとってうれしいことである」と述べておられます。単に、叙事として事実を書くというのではなくて、情感を出すということにこだわりをもって、文章で表現することに打ち込まれたのではないかと思います。
――ありがとうございます。さて、今日は吉田さんご自身が実際に読まれた『ダック・コール』をお持ちいただいております。とても読み込んでおられるようですが、小説を紙の書籍で読む魅力をどのようにお感じですか?
吉田さん:心に響いたところに付箋を立てたり、マーカーを引いたり、自分の字で感想を書きこんだりできるところではないでしょうか。私は中学生の頃から、心揺さぶられた本を二冊買うようになりました。保存用と感想を書き込む用です。自分の字で、読んだときの味わいや読んだ瞬間の気持ちを書きとめておけるのは、紙の本のよいところです。しばらくして読み返したときに、「過去の自分はこんなことを考えていたのか」と振り返ることができ、作品全体とどう向き合ったかが見えてくるんです。紙の本は、昔の自分と対峙できる大切なツールでもあり、書き込みをした本は、ひとつの自分史にもなると思います。